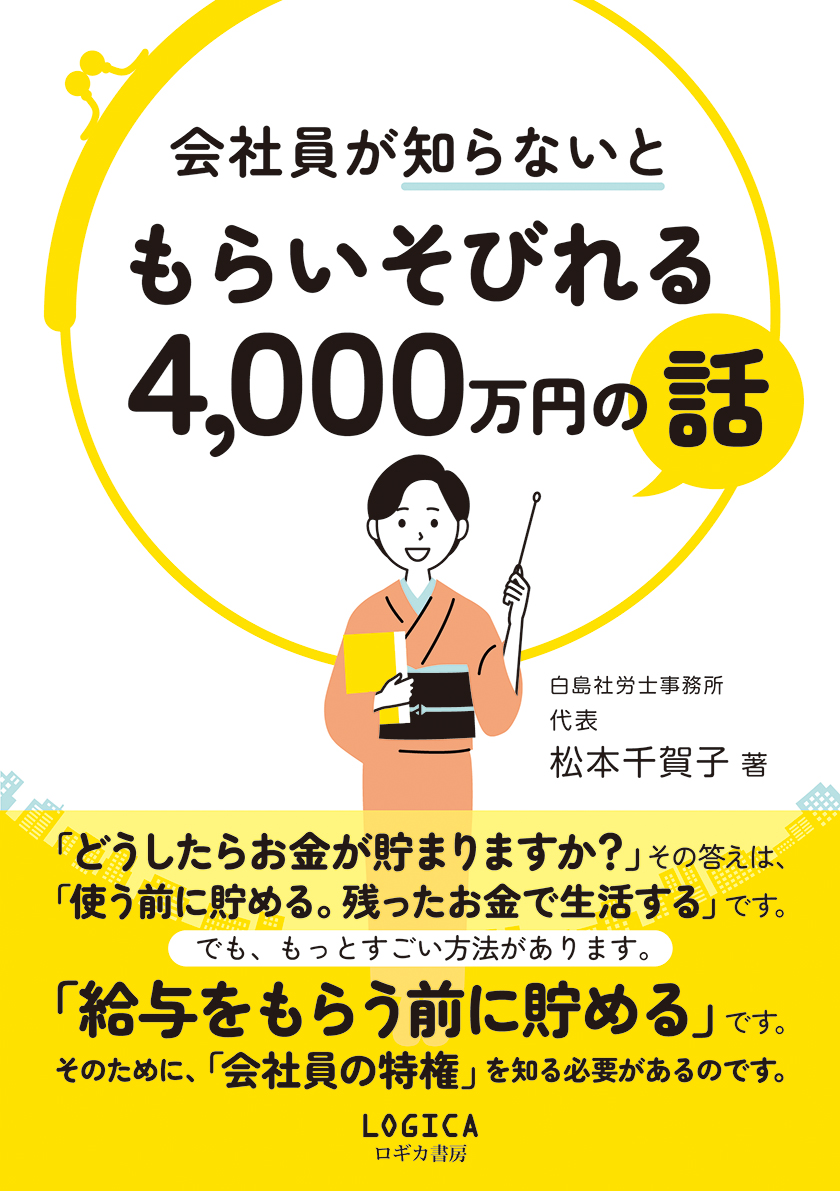|本の詳細
会社員が知らないともらいそびれる4,000万円の話
「どうしたらお金が貯まりますか?」
その答えは、
「使う前に貯める。残ったお金で生活する」です。
でも、もっとすごい方法があります。
会社員の特権を利用して、
「給与をもらう前に貯める」です。
松本 千賀子 著
A5判・176頁(H188×W128×D12 220g)並製
◆定価:本体価格 1,800円+税
◆ISBN978-4-911064-29-0 C0077
◆2025年9月22日発売
◆デザイン:AkiDesign
【著者略歴】
松本千賀子(まつもと ちかこ)
広島大学大学院社会科学研究科経済学修士。外資系生命保険で営業職として勤務(元MDRT 終身会員)の後、独立系ファイナンシャルプランナーとして開業。その後2018年、社会保険労務士資格を取得し広島市に「白島社勞士事務所」を設立。特定社会保険労務士、CFP®、1級FP 技能士、企業年金管理士、DC プランナー2級など複数資格を保有し、株式会社裕和フィナンシャルマネジメントおよび株式会社金融財務研究所の役員も務める。元パーソナルファイナンス教育インストラクターとして小学生から大学等で金融教育に携わる。また、企業型確定拠出年金(DC)の導入支援実績は500社超。現在は広島大学にて「ワークルールと年金・社会保険のしくみ」の客員講師も務めている。趣味は着物、食べ歩き、マラソン。「ゴキゲンな職場づくりとご機嫌なお財布づくり」がモットー。
【内容】
会社員はすごい「特権」を持っています。そのことを知っていますか? 実は、会社員ほど優遇されている人はいないのです。会社員の特権、それは「三種の神器」と言われる、「健康保険」、「厚生年金」、「雇用保険」の3つです。
「なんだ。そんな事か、知っているよ。当たり前じゃないか」と思うかもしれません。ですが、この当たり前のことを正しく理解している人はごく僅かです。そして、この特権は、会社員自らの「請求」あるいは「申請」と「選択」が重要であるということです。あなたが何を選択するか、選択しないかにより、4,000万円以上の差がつくのです。
私はファイナンシャルプランナーとして30年間、多くの方とお話をさせていただきました。その中で一番多い質問は「どうしたらお金が貯まりますか?」です。
その答えはいつも同じです。「使う前に貯める。残ったお金で生活する」です。
給料をもらって、使って、余ったら貯金しようなどということを考える人は、お金が貯まりません。いろいろな節約を試みることはとても大切ですが、節約は結構辛いですよね。楽しんで節約できれば素敵ですね。給与をもらったら先に貯める、これが一番です。
ところが、もっとすごい方法があります。「給与をもらう前に貯める」ことです。財形貯蓄とは全く違います。この方法こそが、知らない間にお金が貯まる究極の方法です。
お金がすべてではありませんが、ある程度のお金がないと不安ですよね。
本書は、会社員の方に「会社員の特権」を知っていただき、そして何より自分自身の「選択」により老後4,000万円を手にしていただきたい、知らないことによる損を減らしてほしいと思い執筆いたしました。この本を手にしていただいた方の、老後やお金に関する不安を少しでも解消することにお役に立てるなら幸いです。
【目次】
はじめに
◆Chapter1 会社員の「三種の神器」プラス2
1 健康保険
(1)健康保険料とそのメリット
(2)傷病手当金と出産手当金
2 厚生年金保険料
(1)厚生年金保険料とそのメリット
(2)障害年金、遺族年金、老齢年金
3 雇用保険料
(1)雇用保険料とそのメリット
(2)基本手当金、育児休業給付金、介護休業給付金
4 プラス2の特権
(1)労働者災害補償保険
(2)退職金制度
◆Chapter2 「選択」で4,000万円の差を生む方法
1 最初の「選択」
(1)企業型確定拠出年金を導入している会社を「選択」
(2)厚生年金加入者しかできない「選択」
2 「選択」できない場合はどうする?
(1)従業員自らが会社に働きかける
(2)ある医療法人の事例
(3)転職者の事例
◆Chapter3 ハイブリッド年金とは
1 ハイブリッド年金(企業型確定拠出年金選択制)の仕組み
(1)企業年金とは
2 確定給付と確定拠出
(1)確定給付企業年金制度とは
(2)企業型確定拠出年金制度とは
(3)基本御制度
(4)選択制
(5)AプラスB
3 ハイブリッド(選択制)年金のメリットとデメリット
(1)メリット1 税制優遇
(2)メリット2 もう1つの効果
(3)デメリット
◆Chapter4 iDeCo/NISA
1 iDeCo
2 NISA
3 iDeCoとNISAの違い
4 NISAとiDeCo どっちが得?
5 iDeCo+
◆Chapter5 4,000万円の効果は「選択」で決まる
1 掛金額の選択
(1)掛金はいくらが正しいのか
(2)社会保険料と掛金額の選択
2 運用商品の選択
(1)元本確保型商品
(2)元本変動型商品
(3)どの商品を選択するか?
3 受け取り方の選択
◆Chapter6 導入サポート会社の選択
1 制度導入の流れ
(1)最初の掛金拠出まで最短で6か月程度かかる
(2)iDeCoからの移管 136
2 導入後の違い
(1)制度説明
(2)サポート/教育
◆Chapter7 終わりに~さようなら辛い節約生活
1 気づいたら貯金ができていた
2 三種の神器を知れば家計も変わる
3 忘れてはいけない「請求」、「申請」、「選択」
◎奥付情報
印刷・製本 亜細亜印刷株式会社
初版発行 2025年10月20日