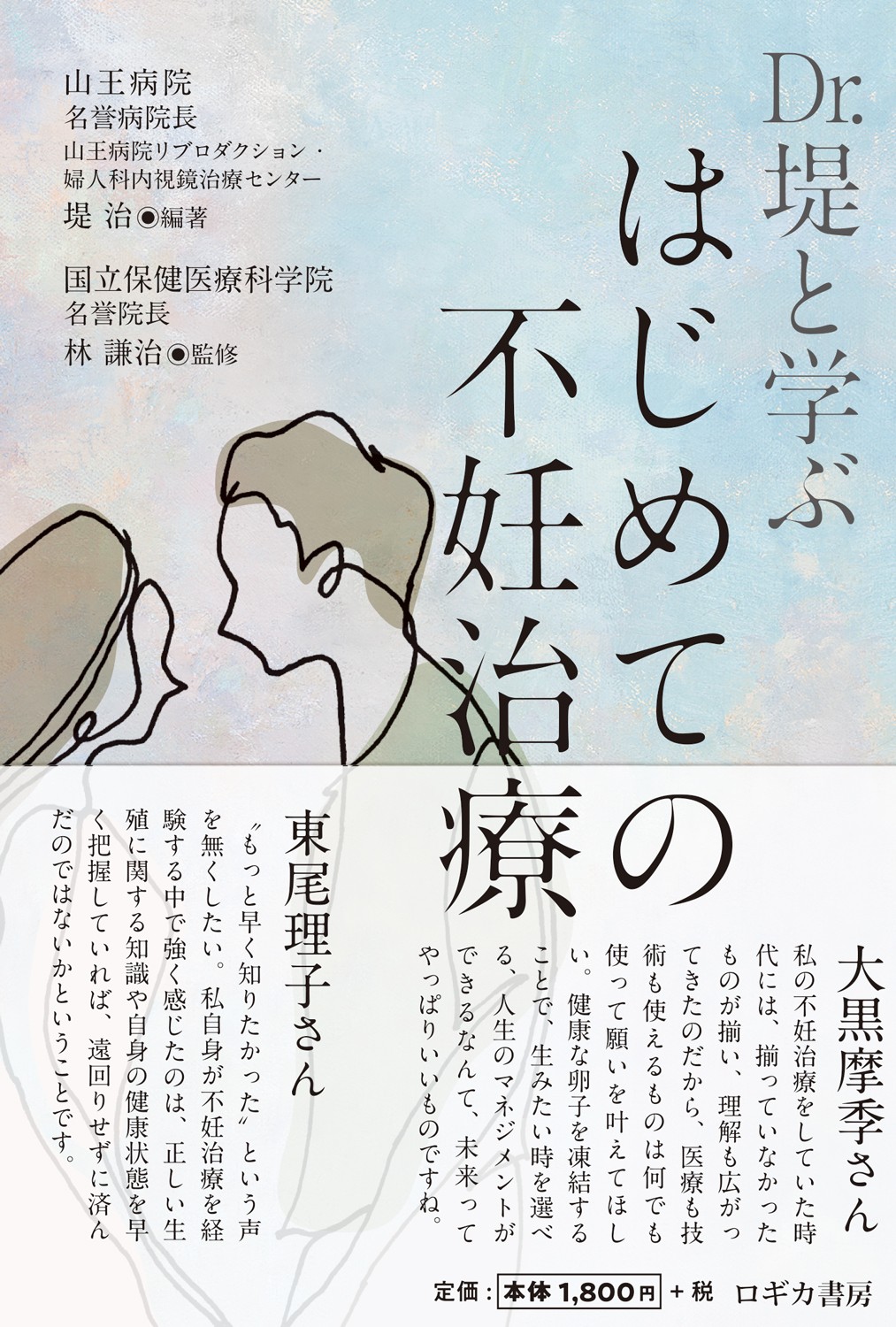|本の詳細
Dr.堤と学ぶ はじめての不妊治療
シンガーソングライター 大黒摩季さん
健康な卵子を凍結することで、産みたい時を選べるなんて、本当に素晴らしい。
プロゴルファー 東尾理子さん
‶もっと早く知りたかった〟という声を無くしたい。
堤 治 編著
林 謙治 監修
四六判・208頁(H188×W128×D12 250g)並製
◆定価:本体価格 1,800円+税
◆ISBN978-4-911064-28-3 0047
◆2025年9月14日発売
◆デザイン:Izumiya
◆イラスト:大野まみ
【著者略歴】
(編著者プロフィール)
堤 治(つつみ おさむ)
山王病院名誉病院長
山王病院リプロダクション・婦人科内視鏡治療センター
埼玉県秩父市出身、東京大学医学部を卒業後生命誕生に憧れて産婦人科医に。
不妊症を専門とし1979年から卵子研究に従事。米国国立衛生研究所(NIH)留学、東京大学大学院教授を経て、2008年より山王病院病院長、国際医療福祉大学大学院教授。
現在、山王病院名誉病院長としてリプロダクション・婦人科内視鏡センターで不妊治療、内視鏡手術、出産などを幅広く行い、難治性不妊の治療にも熱意をもって取り組んでいる。
元東宮職御用掛で皇后雅子さまの愛子さまご出産に際し主治医を務めた。アジアパシフィック婦人科内視鏡学会、日本産科婦人科内視鏡学会、日本受精着床学会などの理事長を歴任、日本を代表する産婦人科医の1人。
(監修者プロフィール)
林 謙治(はやし けんじ)
1971年 千葉大学医学部卒業、医学博士、成田日赤病院、千葉県松戸市立病院産婦人科勤務を経て、1978年厚生省国立公衆衛生院母性小児衛生学部研究員
1980年 科学技術庁派遣在外研究員、米国Yale大学医学部研究員(周産期疫学専攻)
1981年 国立公衆衛生院母性小児衛生学部学校衛生室長
1986年 同院保健統計人口学部部長
2002年 国立保健医療科学院(組織再編により改称)次長
2009年 国立保健医療科学院院長
2012年 国立保健医療科学院名誉院長
専門分野 母子保健政策、地域保健、保健統計、国際保健
在任中 厚生労働省各種専門委員会座長を務める。
国際的にはWHO高度保健統計専門委員、フランス国立人口研究所研究員、アジア太平洋公衆衛生学校理事長、世界公衆衛生学校会議日本代表を務める。
2016年 日本産前産後ケア・子育て支援学会理事長現在にいたる。
【内容】
みなさまこんにちは。産婦人科医として40年以上不妊治療に取り組んでいる堤治と申します。この本を手に取って頂いているみなさまの多くは、ご自分が不妊症ではないかと悩まれたり、不妊治療に取り組もうとされていると思います。不妊を心配されるご夫婦は26組に1組、実際に不妊治療を受けたことがあるご夫婦は4.4組に1組とけっしてまれなことではありません。
本書の目的とするところは、みなさまの疑問に答えながら妊娠する仕組み、不妊の原因や治療法などをご理解頂き、不妊治療の敷居を下げて受診してみようかなと思って頂こうというものです。もしかしたら、この本を読んだだけで、「そうだったのか」と自然妊娠される方もおられることも期待しながら話を進めてまいります。
各章の最初にそれぞれの章のねらいとそこで知って頂きたい疑問点をQ&Aという形でお示しします。不妊外来でお話していると患者さんに「もっと早く知っておきたかった。どうしてもっと早く教えてくれなかったのですか」と言われることが少なくありません。初診ではじめてあった方には教えようがありませんが、みなさまにはぜひ、読み進みQ&Aにご自分でお答え頂けるように読み込んで頂ければ幸いです。
不妊治療を大きく分けると一般不妊治療と生殖補助医療の2つがあります。流れとしては一般不妊治療が先行し、よい結果が得られない場合体外受精などの生殖補助医療が適応となります。生殖補助医療は保険適用にもなり体外受精で生まれた子どもは年間7万7千人、日本で生まれる子どもの9人に1人を占めています。生殖補助医療は大きな成果を上げる一方、光と影でなかなか妊娠が成り立たない難治性不妊が浮かびあがっています。本書でも解説させて頂き最新の治療法についてもお話します。
不妊治療をより立体的にご理解頂けるように、本書にご協力下さった方々がおられます。8章はみなさまご存じのシンガーソングライターの大黒摩季さんが子宮筋腫・子宮内膜症・子宮腺筋症に苦しみながら不妊診療に取り組んだ経過を患者さんの目線でお話くださいます。9章はご自身の不妊治療経験から東尾理子さんが立ち上げたNPO法人TGPの取り組みを紹介くださいます。林謙治先生は産婦人科医ですが、厚生行政にもお詳しく、10章「少子化と生殖医療をめぐる社会環境の変化」を執筆くださいました。
前置きはこれだけにして、第1章「妊娠のなりたつしくみに」進んでいきましょう。
【目次】
はじめに
監修のことば
●第1章 妊娠のなりたつしくみ
Q1卵子は年をとると聞きました。どういう意味ですか?
Q2精子はいつも生まれたてで、運動能力が大事とは、どういう意味でしょう?
Q3卵子と精子の出会いは、タイミングが大事で、卵管の限られた場所というのは?
卵子の秘密⁉/排卵―卵子のめざめ/やんちゃな精子/受精の瞬間/着床から妊娠へ/知っておきたいウイルスの知識
●第2章 不妊症を知ろう
Q1不妊症の定義みたいなものはありますか?
Q2不妊症の原因は、男性と女性どちらにありますか?
Q3不妊症は最近、増えていますか?
不妊症の定義/加齢と不妊症/不妊に関係する疾患/不妊症理解のポイント/不妊症の3因子/女性不妊症/エストロゲン依存性疾患/男性因子/不妊原因のポイント
●第3章 不妊の検査はこわくない
Q1不妊の検査や治療は、どこで受けられますか?
Q2排卵があるか、いつ排卵するかは、どうしたらわかりますか?
Q3男性の検査は、どのようにするのでしょうか?
Q4卵管の検査は痛いと聞きました、大丈夫でしょうか?
不妊症の検査治療はどこで⁉/妊娠・不妊を左右する3大因子7/排卵・卵巣因子/卵管因子2/男性因子
●第4章 不妊治療の基本
Q1タイミング法が基本と聞きました。どうするのでしょうか?
Q2人工授精と体外受精は、どう違いますか?
Q3不妊症にも内視鏡が使われると聞きました。どのような治療がおこなわれますか?
タイミング法/人工授精/内視鏡検査・治療
●第5章 高度不妊治療―体外受精の実際―
Q1体外受精は、どのような治療法で、どのような場合におこなわれますか?
Q2排卵誘発の、母体への危険性や胎児の異常は、心配ありませんか?
Q3保険診療が適用されたということですが、どこまで保険でできますか?
体外受精が必要な場合/体外受精治療の流れ/排卵誘発法/採卵と授精/受精卵の発育と胚移植/卵巣過剰刺激症候群の予防と対処/不妊治療の保険適用
●第6章 難治性不妊とたたかう
Q1胚に原因がある場合は、どのような問題があり、対応はどうしますか?
Q2子宮内膜に原因がある場合は、どのような問題があり、対応はどうしますか?
Q3予防することはできませんか?
胚に原因がある難治性不妊/染色体異常のできるわけ/胚による難治性不妊の療・予防はありますか?/子宮内膜に原因がある難治性不妊/難治性不妊の原因と予防
●第7章 プレコンセプションケアが少子化への処方箋⁉
Q1プレコンセプションケアとはなんで、どうして少子化対策になるのですか?
Q2卵子凍結もプレコンセプションケアですか?
Q3プレコンセプションケアで、命が救われることがありますか?
プレコンセプションケアとは/日本の生殖医療の現状/卵子凍結という選択/プレコンセプションケアで救われる命
●第8章 大黒摩季さんとの対談
Q1大黒摩季さんが経験した子宮腺筋症・子宮内膜症・子宮筋腫とは?
Q2難治性不妊の治療戦略は、どうあるべきか?
Q3卵子凍結という選択は?
●第9章 NPO法人TGPの取り組み
当事者支援への想いとその背景/支援事業の紹介
●第10章性と生殖の知識
女性の生殖器/男性の生殖器/性反応
●第11章 少子化と生殖医療をめぐる社会環境の変化―ミクロの視点からマクロ政策をみる―
はじめに/リプロダクティブヘルスから生殖医療への進化/リプロダクティヘルスの前景―私の医療体験―/ヘルスリテラシー教育を考える/「プレコンセプションケア」は「ヘルスリテラシー」の推進が前提/少子化の位相を分析する/政策としてのリプロダクティブヘルス・ライツ/最後に
おわりに
◎奥付情報
印刷・製本 藤原印刷株式会社
初版発行 2025年9月30日